「できません」「わかりません」。
何気なく口にするこの言葉に、どれほどの重さがあるか、立ち止まって考えたことはありますか。
私たちは、日常の中で無意識のうちに“思考のブレーキ”を踏んでいます。
ほんの小さな「できない」というつぶやきが、頭の中で広がり、
気づけば、可能性という名の道を一本ずつ閉ざしていく。
それは決して怠け心からではありません。
むしろ、自分を守るための無意識の防衛反応に近い。
失敗したくない、責められたくない、恥をかきたくない。
そんな不安や恐れが、私たちの口を借りて「できません」と言わせているのです。
けれど、その一言が、どれほど多くの会話を止めてきたかを思うと、
少し胸が痛くなります。
せっかくのチャンスが静かに遠のき、
相手との距離が一歩、また一歩と開いていく。
そして、何よりも悲しいのは――その言葉が自分自身との対話までも止めてしまうことです。
「できない」と言った瞬間、思考は静まり、心の中の探究が終わります。
可能性を探す前に、結果を決めてしまう。
だからこそ、ほんの少しだけ意識を変えてみてほしいのです。
もし、次にその言葉が喉まで出かかったら、一呼吸おいてみる。
そして、自分に問いかけてみるのです。
「本当に、できないのだろうか?」
そう思考を続けてみるだけで、関係の空気は変わります。
人との距離も、言葉の温度も、結果さえも変わっていく。
“できない”を封じることは、
無理をすることではなく、考え続ける勇気を持つこと。
それは、誰かとつながるための小さな一歩であり、
同時に、自分の人生を少しずつ動かす力でもあるのです。
「できない」は、思考を止める言葉
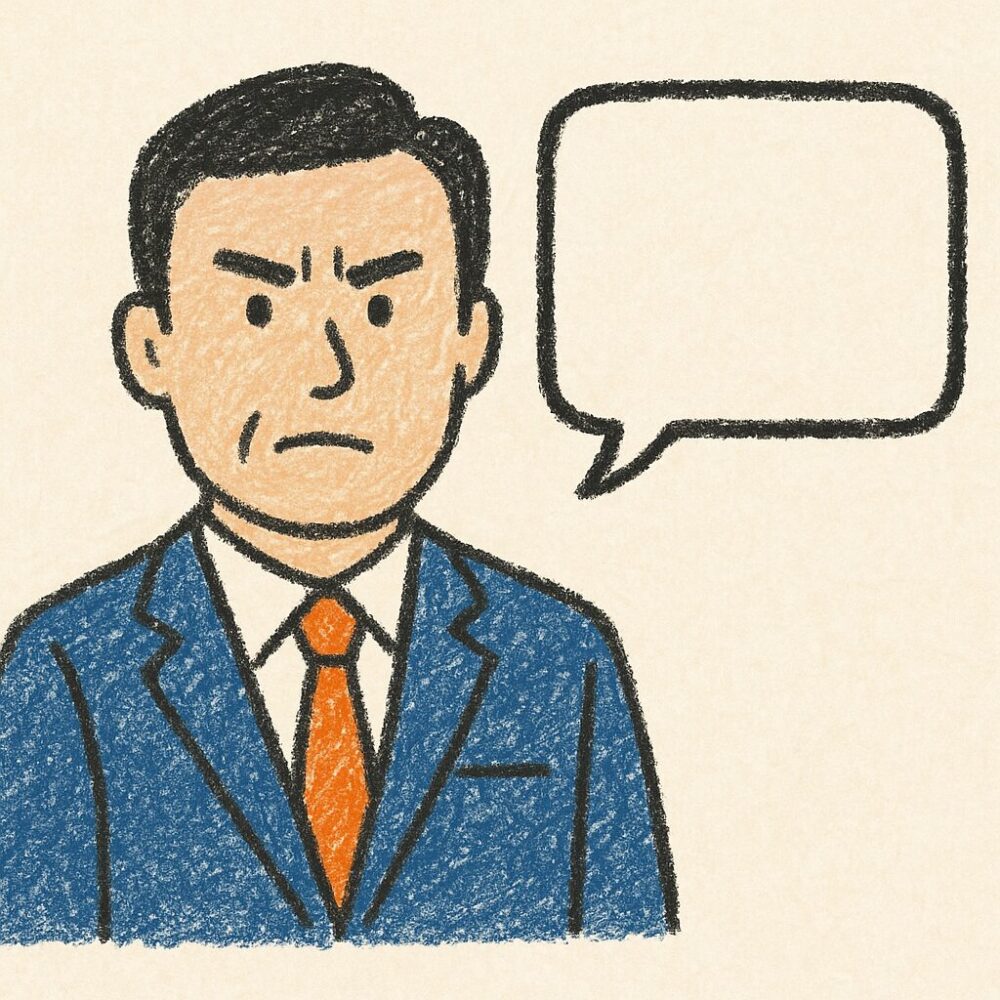
職場で、部下から「できません」と言われたとき。
それは決して悪気のある言葉ではないのに、不思議と心に引っかかるものです。
もしかしたらその瞬間、あなたも感じたことがあるかもしれません。
「努力する気がないのかな?」
「もう少し考えてみてほしいな」
私自身もそう感じてきました。
そして気づいたんです。
この言葉の問題は、“否定”ではなく“停止”にある、と。
「できない」と言った瞬間、思考が止まる。
相手の頭の中で、課題のドアが音もなく閉じてしまうんです。
だから私は、言葉を変えようと決めました。
「できない」ではなく、「どうしたらできるか」。
これは、自分にも部下にも、そっと投げかける小さな問いです。
「それ、本当にできないのかな?」
「もし時間ややり方を変えたら、できるかも?」
強く叱る必要なんてありません。
問いかけるだけで、止まっていた思考が動き始めることがあります。
親と子も同じ。感情の奥にある「できない」
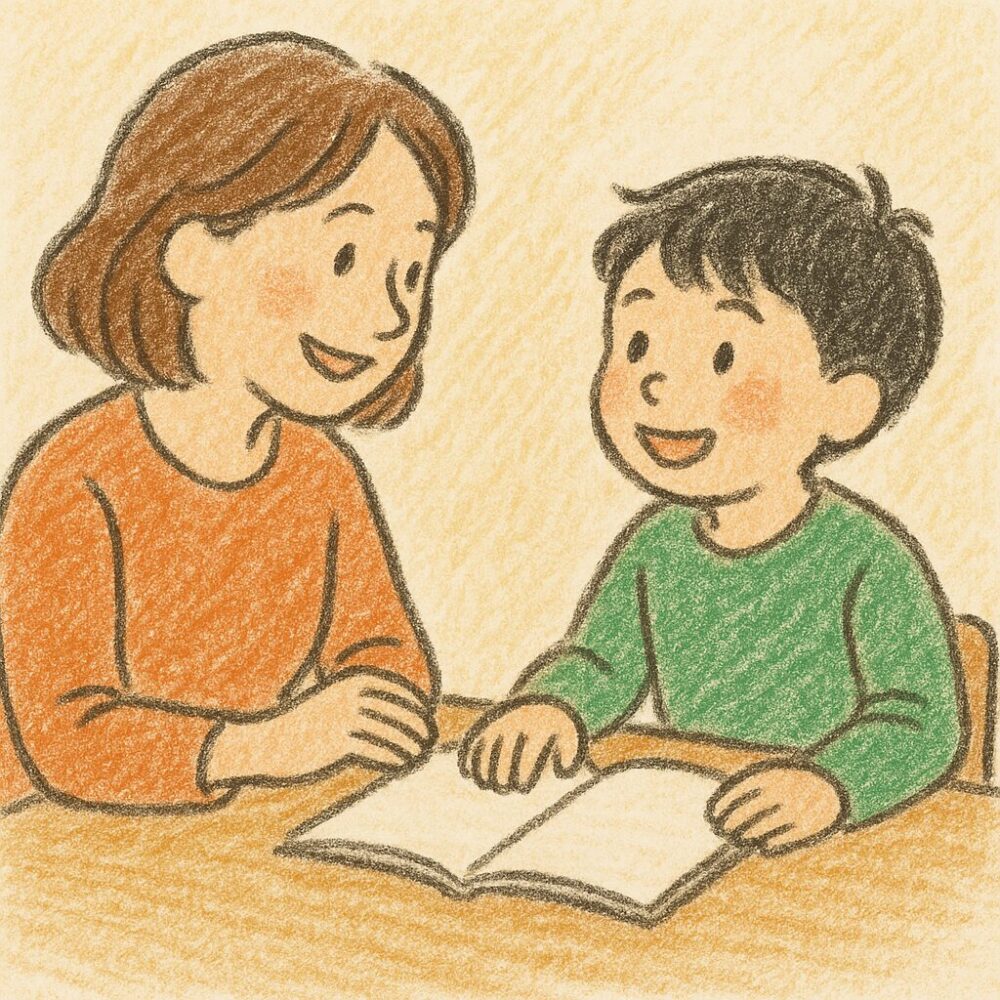
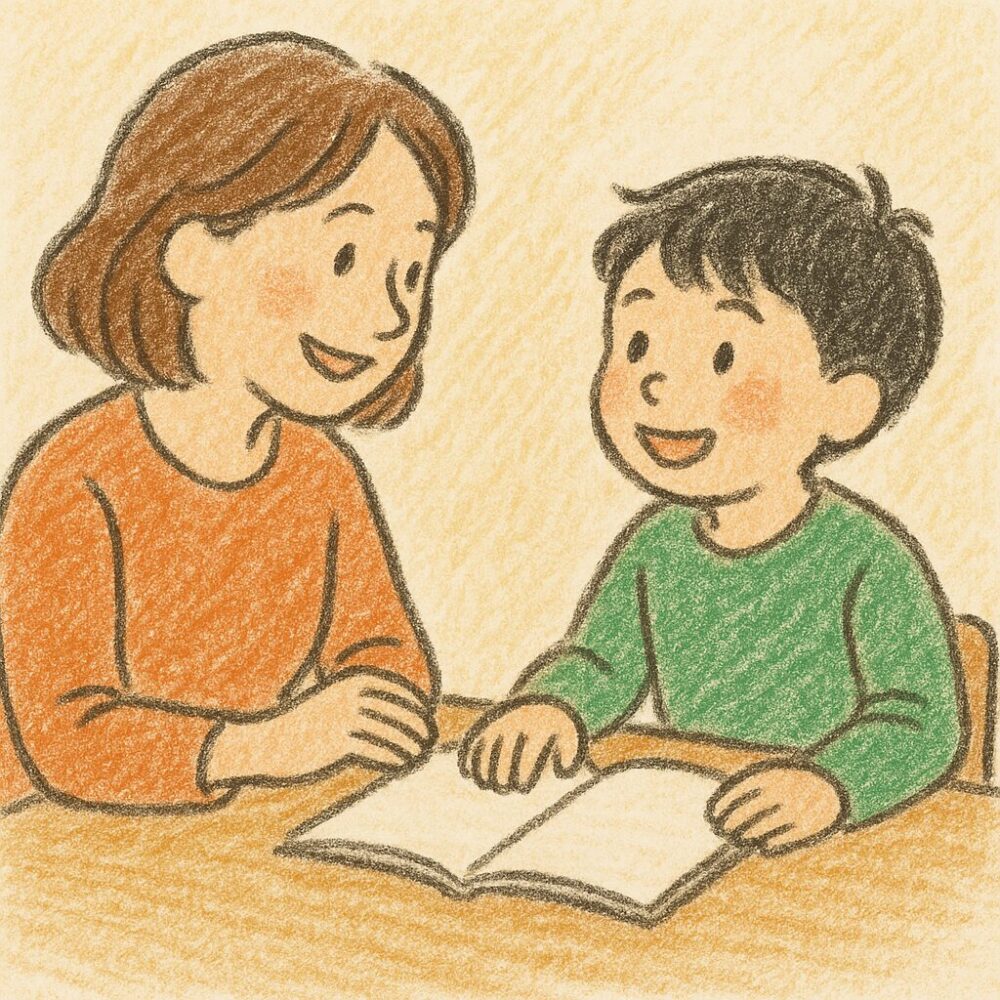
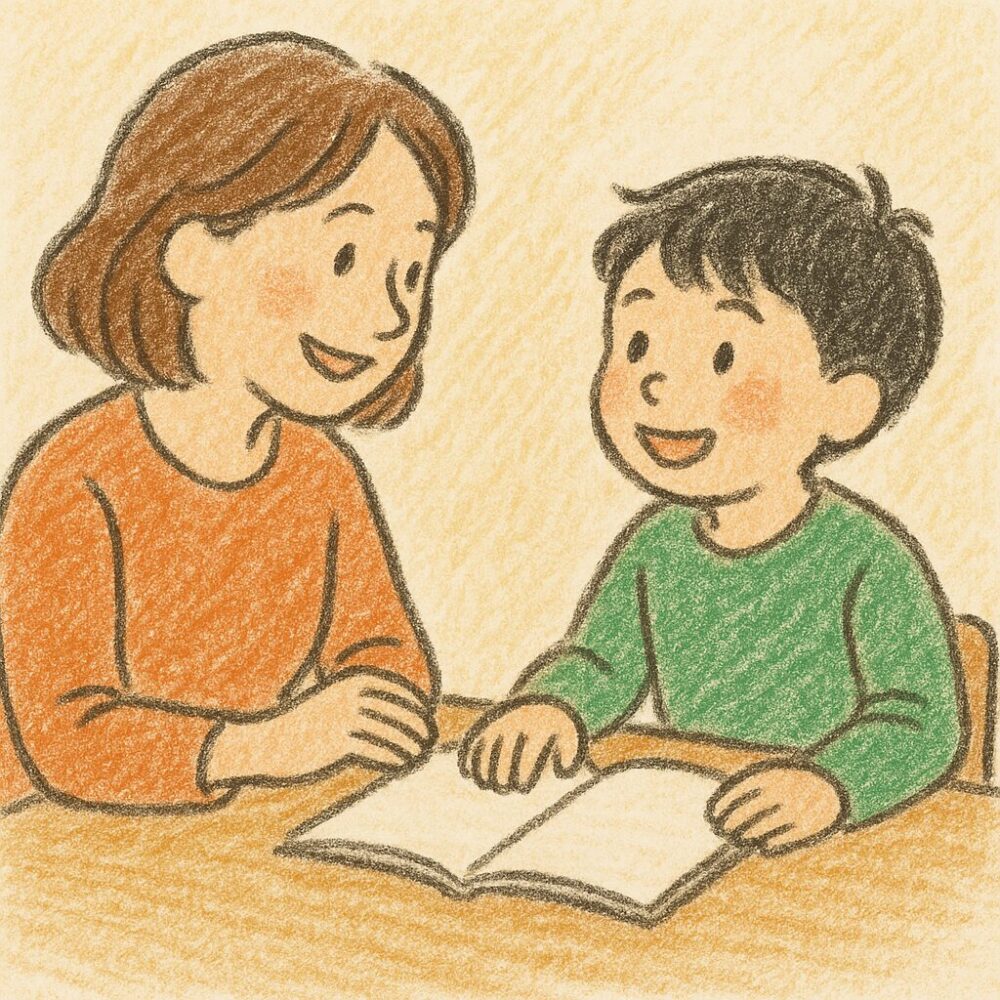
家庭では、子どもの「できない」が別の形で現れます。
「勉強いやだ」「わからない」「もうムリ」──。
それを聞くと、忙しい大人の私たちはつい言ってしまうんです。
「そんなこと言わないの」
「やればできるって」
けれど、子どもが伝えたいのは“結果”ではなく“気持ち”なんですよね。
不安だったり、悔しかったり。
ただ、それをうまく言葉にできないだけ。
私も親として、つい反射的に「できないで済ませるな」と言ってしまうことがあります。
けれど、あとで反省します。
本当は、励ますよりも、気持ちを受け止めることが先なんです。
「思ったようにいかなくて悔しいよね」
「うまくできなくて、少し怖くなっちゃったのかな」
この一言で、子どもの表情が少しだけ緩む。
その瞬間、「次はやってみようかな」という意欲が、静かに芽を出します。
「できない」を封じる朝の習慣
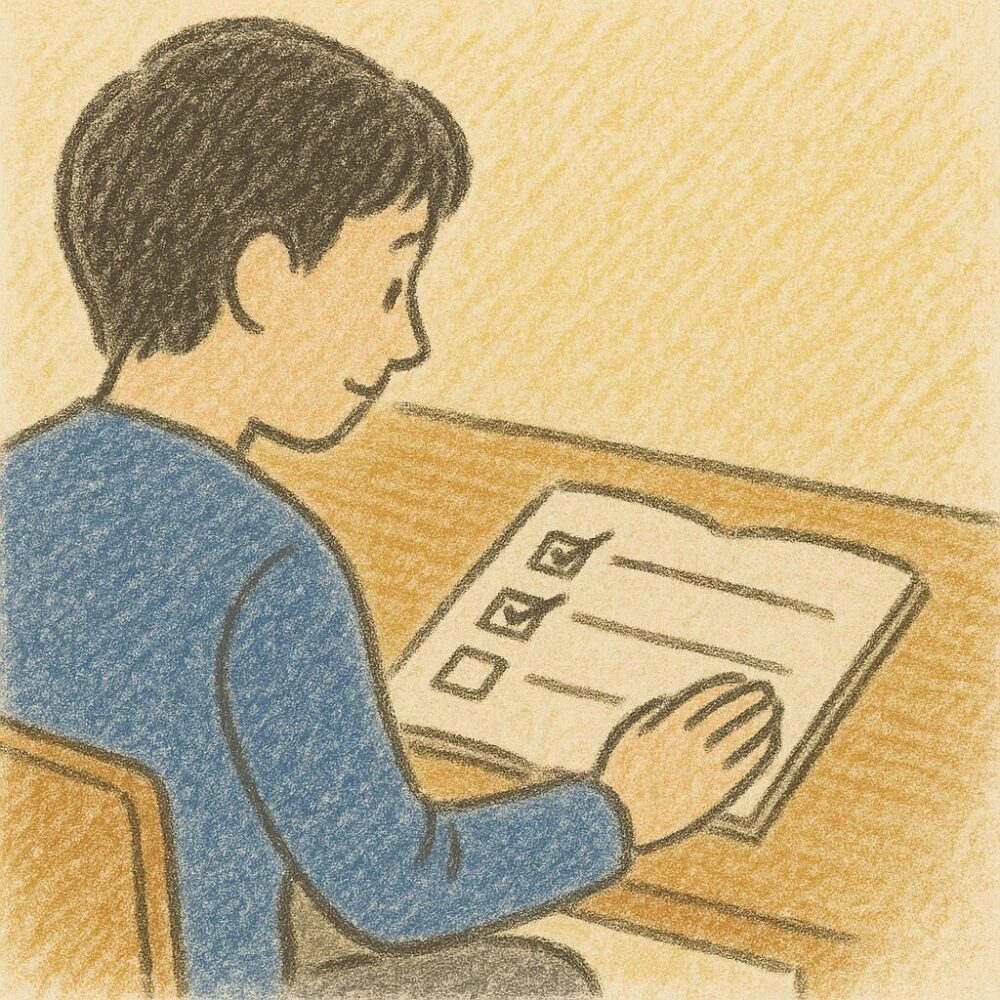
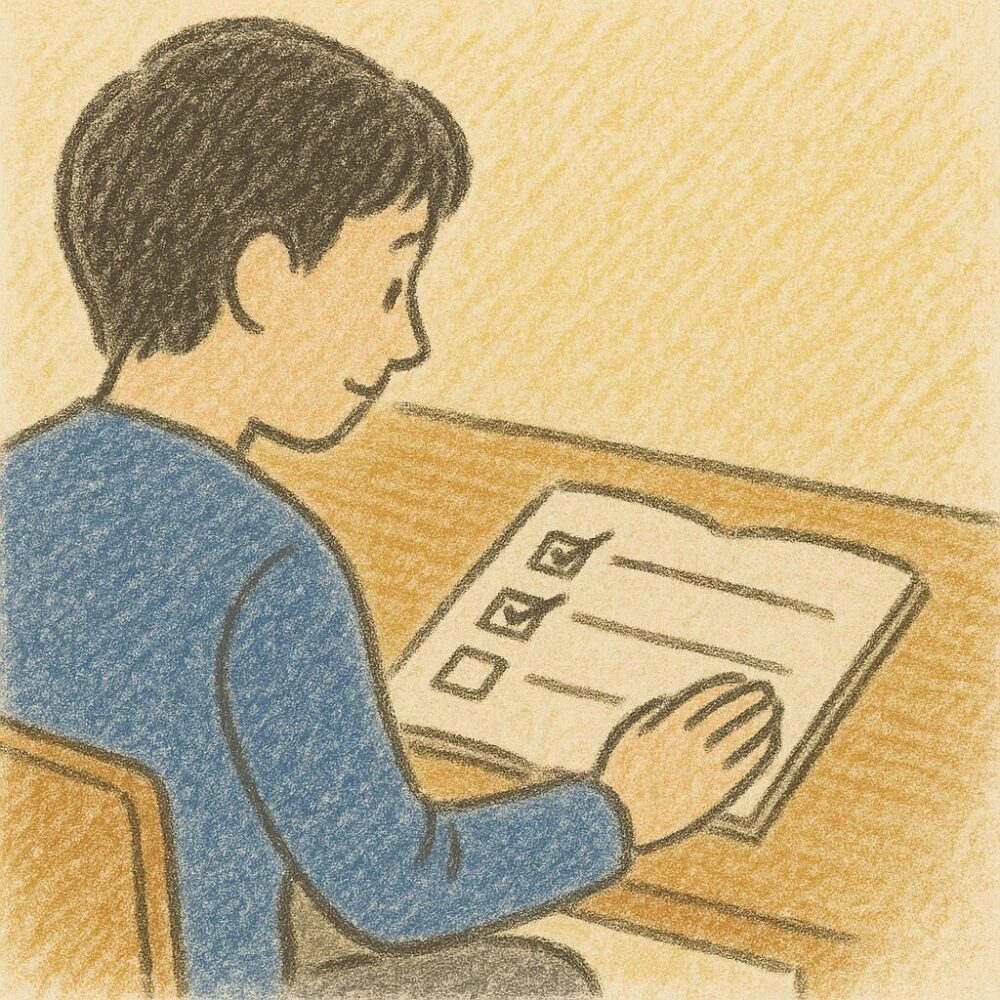
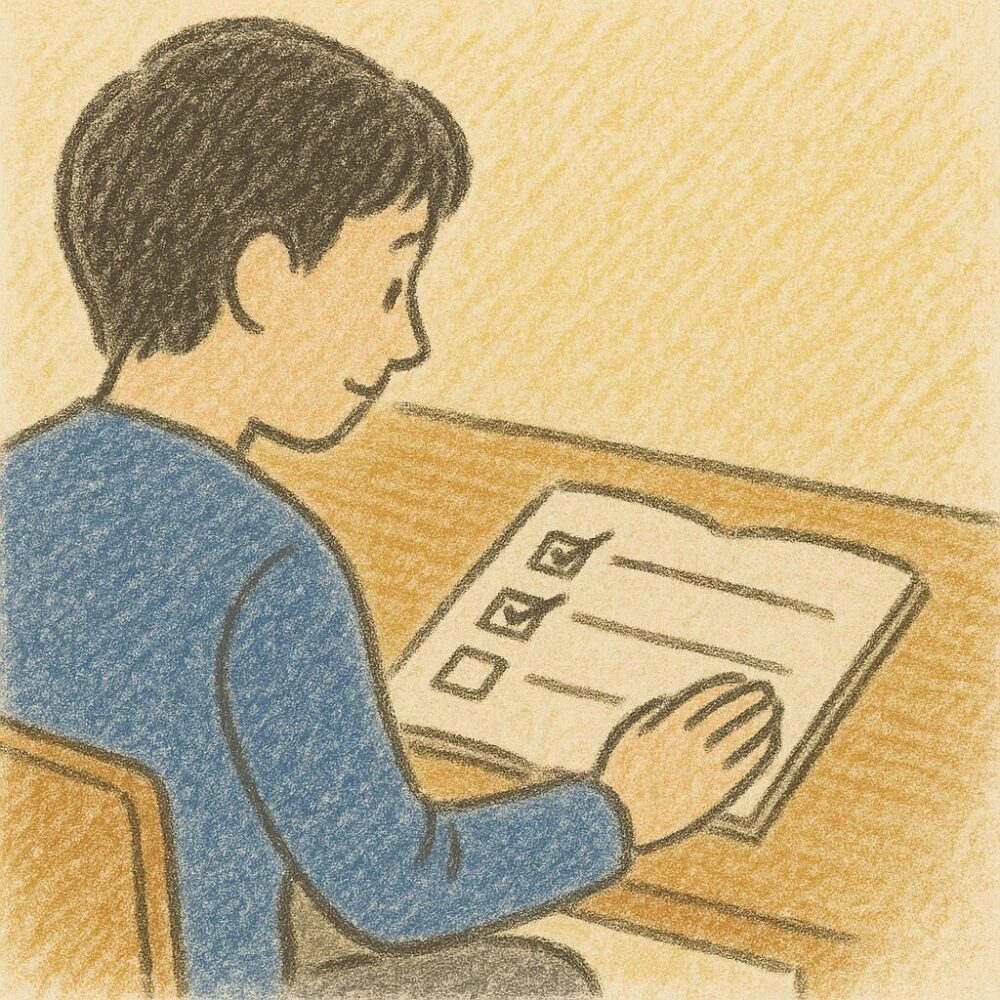
私は毎朝、目標達成リストを見返しています。
そこには小さく、けれど力のある言葉を書いています。
「できない・わからないを言わない」
たったこれだけ。
でも、この一文が、毎日の考え方をリセットしてくれるんです。
朝の静かな時間にその言葉を読むと、自分に問いかけが始まります。
「この問題は本当に解決できないのか?」
「時間やお金をかけたら、道は開けるのではないか?」
思考を止めないというのは、根性論ではありません。
それは、自分の可能性を“探し続ける習慣”です。
考え続ける人が、信頼を積み重ねる



「できない」を封じるというのは、我慢ではありません。
それは、**逃げずに考え続けるという“選択”**です。
上司も、部下も、親も、子も──
人と向き合う時間の中には、思うようにいかない瞬間が必ずあります。
相手が理解してくれない。話がすれ違う。
努力が報われない。
そんなときにこそ、“できない”という言葉が頭の中に浮かびます。
でも、その一言をぐっと飲み込み、もう少しだけ考えてみる人がいます。
感情に流されず、言葉を選びながら、相手の意図を汲もうとする人。
それが、「考え続ける人」です。
彼らは、派手に主張しなくても、周りの人を安心させる存在です。
なぜなら、「あの人はすぐに諦めない」「最後まで話を聞いてくれる」と、
人々が心のどこかで信じているからです。
考え続ける人は、沈黙の中でも誠実さを伝える。
相手の言葉を止めずに、考えを引き出し、
自分の感情を閉ざさずに、想いを伝える。
その繰り返しが、やがて信頼を積み上げていきます。
チームの中で誰かが意見を出したとき、
「それは違う」とすぐに否定せず、「なぜそう思ったの?」と聞き返す。
家庭で子どもが言い訳をしたとき、
「どうしてそう感じたの?」と静かに尋ねる。
その一言が、空気を変えます。
相手は“責められた”ではなく、“受け止められた”と感じる。
その安心感が、次の一歩を生み出すのです。
思考を止めないということは、相手に信頼のバトンを渡すこと。
「この人になら話してみよう」
「この人となら、もう一度挑戦できる」
そんな関係が、少しずつ積み重なっていく。
そういう人が、声を荒げることなく、静かにチームを動かします。
命令ではなく、共鳴で人を動かす。
力ではなく、言葉の温度で空気を変える。
そしてその姿勢は、家庭でもまったく同じです。
家族の中で、子どもやパートナーが落ち込んでいるとき、
無理に励ますよりも、そっと話を聴いてくれる人。
焦らず、怒らず、相手が自分で答えを見つけるまで見守る人。
その存在が、家庭を温めていきます。
考え続ける人は、どんな場所でも、静かに信頼を積み重ねる。
その信頼は、声を荒げるリーダーシップよりもずっと深く、長く、人の心に残る。
“できない”を封じて考え続けること。
それは、他人を動かす技術ではなく、人を信じる覚悟の表れなのです。
言葉を変えると、関係が変わる



「できない」と言いたくなる瞬間は、誰にでもあります。
私にも、何度もありました。
仕事で壁にぶつかって、思わず「無理だ」とつぶやいた夜。
子どもに同じことを何度も注意して、ため息をついた朝。
それでも、後になって思うのです。
あの“できない”という言葉には、あきらめの気持ちよりも、自分を守ろうとする小さな悲鳴が隠れていたのだと。
ほんの少し、立ち止まってみる。
深呼吸をして、「本当に無理だろうか?」と問い直してみる。
たったその一呼吸で、見える景色が変わる瞬間があります。
思い込みが少しゆるみ、誰かの顔が浮かび、「やってみよう」という気持ちがわずかに灯る。
そんな経験を重ねていくうちに、人は少しずつ強く、そして優しくなっていくのだと思います。
言葉を変えることは、単なる言い換えではありません。
それは、自分の心の姿勢を変えること。
「できない」と口にした瞬間に閉じていた扉を、
「どうすればできるか」と問い直すことで、もう一度開く。
そこに生まれるのは、行動の余地だけでなく、人との対話の余白です。
不思議なもので、自分が変わると、周りも変わっていきます。
部下が少し前向きな提案をしてくれたり、
子どもが「もう一回やってみる」と笑顔で言ってくれたり。
その変化を目の当たりにするとき、言葉の力の大きさに胸を打たれます。
言葉は人を動かします。
そして、人を動かす言葉は、いつだって思考の中から生まれる。
考えることをやめない人、思考を止めない人は、どんな関係の中でも信頼を積み重ねていきます。
人生は、結局のところ“対話”の連続です。
他人との対話、そして自分との対話。
「できない」という言葉をひとつ封じるだけで、その対話の流れが変わる。
その変化は小さくても、積み重なれば確実に人生を動かします。
言葉を変えると、関係が変わる。
関係が変わると、世界の見え方も変わる。
そして、そのすべての始まりは、あの日、自分が「できない」と言いかけて立ち止まった、たった一瞬の勇気なのです。

コメント