建設業界に身を置いていると、「資材価格の高騰」「人材不足」「公共工事の単価改定」など、外部からの影響を常に受ける。そんな中で、“ただ指示通りに動く”だけの働き方では限界があることに気づくはずだ。
厚生労働省の 令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概要 によれば、2024年中に賃金を改定した建設業の企業は、そのほぼすべて(99.7%)が賃上げを実施しており、平均賃金改定額は約 15,283円、前年比 4.3% の上昇となっている。さらに、国土交通省が令和6年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、令和7年3月から適用される公共工事設計労務単価は、全国全職種の単純平均で 前年度比5.9%引き上げ られた。これは令和5年度の消費者物価指数(前年比3.2%)を上回る伸びである。
一見すると追い風だが、「成果を出した人が報われる」ことと、「制度上の賃金が上がる」ことは別問題だ。現場の実感は必ずしも統計と一致しない。だからこそ、事業主のように「収益」「コスト」「価値」を自分で意識して動けるかどうかが、今後のキャリアを左右するのだ。
建設業は「人の手でしかできない仕事」が多く残っている分、スキルや判断力の差が成果に直結する。つまり、事業主マインドを持つ社員と持たない社員とでは、将来的に大きな差が開いていくのだ。
現場の声:“利益を出しても報われない”という不満
私の部下が、膨大な利益を上げた案件があった。議事録担当として役員会で報告した際、その部下は「成果に応じたインセンティブが欲しい」と率直に訴えた。しかし、役員の答えは明快だった。
「インセンティブを与えるなら、ペナルティも必要になる。だから制度としては導入しない」
この言葉に私は納得した一方で、部下のモチベーションが一気に冷めていく様子も感じた。現場では「頑張っても意味がない」という空気が広がりやすい。
経営の視点から見れば、報酬制度を動かすには法的制約や組織全体のバランスがあり、そう簡単には変えられない。しかし現場の人間からすると、努力と報酬が結びつかないことは大きな不満となる。
建設業は体力的にも精神的にもハードな現場が多い。だからこそ「頑張りが正当に評価されない」と感じると、一気にモチベーションが落ちてしまう。この不満の構造を理解したうえで、個人としてどう動くかが重要になるのだ。
気づいていない恩恵:会社員の安定性
私は父が自営業(大型冷凍機の販売・修理、空調工事)をしていたため、幼い頃から「事業主のリスク」を目の当たりにしてきた。父は1人で事業を切り盛りし、ときには 1,000万円以上の現金を集金 することもあった。
その額の大きさに驚きながらも、同時に「収入が安定しない現実」も知った。案件が入らない月は収入が途絶える。逆に大口の仕事が入れば一時的に潤う。ジェットコースターのような収入の波を家族は耐えなければならなかった。
だからこそ、私は会社員の「給料が下がらない」という仕組みのありがたみを強く実感している。建設業であっても、会社が赤字になっても毎月決まった給与が支払われる。リスクとリターンの非対称性。この安定性こそ、サラリーマンの最大の恩恵なのだ。
建設業界では資材価格の高騰や人材不足により、経営基盤が揺らぐ企業も少なくない。そんな状況でも給与が守られるのは、雇用契約という強固な仕組みがあるからだ。事業主目線を知っているからこそ、この安定がどれほど価値あるものかが理解できる。
“雇われマインド”からの脱却ポイント
会社員でありながら事業主マインドを育てるには、まず「ないもの探し」をやめ、「得ているもの」に目を向ける必要がある。
与えられないことではなく「得られていること」を意識する
賃金やインセンティブの不足に目が行きがちだが、安定した給与や社会保険、福利厚生はすでに享受している恩恵だ。これを認識するだけでも、見える景色が変わる。
インセンティブ以外で得られる成長や信用
報酬だけでなく、スキル・人脈・信頼は長期的に見れば大きな資産となる。私自身、レスポンスの早さを徹底することで信頼を獲得してきた。特別に褒められることはなかったが、他の人より早いという事実だけで、1ヶ月も経てば現場の人間は自然と私の指示を聞くようになった。これこそ“信用”の力だ。
小さな改善が会社全体に与えるインパクト
現場での効率化やコスト削減は、会社全体の利益に直結する。例えば、資材の仕入れ先を見直すだけでも数十万円単位のコスト削減が可能だ。自分の工夫が組織にどう影響するかを意識できる人は、評価されやすい。
事業主マインドを育てる習慣
建設業で働きながら「事業主マインド」を養うためには、日々の業務で次の習慣を意識することが効果的だ。
利益とコストを数値で意識する
材料費、人件費、外注費などを数字で把握し、常に「この仕事はいくら利益を生んでいるか」を意識する。時間もコストと捉える習慣をつければ、無駄が見えてくる。例えば残業を減らす工夫も「人件費削減」という立派な利益向上策になる。
さらに大事なのは、ものの単価だけではなく自分の時間もお金として換算し、トータルでコストとして考えることだ。資材の原価だけを見て「安い・高い」と判断しても不十分で、そこにかかる労働時間や移動時間まで含めてこそ、真のコスト管理になる。時間=お金という意識を持つことで、より経営者に近い視点を養える。
「もし自分が経営者なら?」と考える
一つひとつの判断に「自分が経営者ならどうするか」と問いを立てるだけで、視野が変わる。たとえば公共工事の契約交渉や価格転嫁の場面では、経営者目線を持つことが成果につながる。
成果を可視化し、チームで共有する
建設業はチームワークが命。自分やチームの成果を数値や実績として見える化し、社内で共有することで、擬似的なインセンティブを得られる。評価が制度に直結しなくても、達成感や信頼は積み重なる。
例えば、工期を短縮できたことを数字で示せば「コスト削減」だけでなく「顧客満足度の向上」にもつながり、現場全体の士気を高められる。
まとめ:守られていることに感謝しつつ、事業主として考える
建設業はコスト高騰や人材不足など課題を抱えつつも、賃上げの流れが加速している。サラリーマンとして守られた立場にある一方で、その恩恵に甘えるだけでは成長は止まる。
安定と挑戦、その両方を理解しながら動くこと。
モチベーションは“外から与えられるもの”ではなく、自分で設計するものだ。
現場の厳しさを知るからこそ、守られている安定のありがたさを感じられる。そして、挑戦の先にこそ本当の成長がある。自分の時間も労力も「投資」と捉え、未来の自分に回収させる意識を持ってほしい。
事業主マインドを持つことで、建設業界においても一歩先を行く働き方ができる。これは現場での信用を高め、キャリアを伸ばし、最終的には自分自身の「稼ぐ力」を強化する最短ルートになるだろう。
守られていることに感謝しつつ、挑戦を恐れず歩む。その姿勢が、自分の人生を強くしなやかにしていくはずだ。
事業主マインドを持つことは、特別な才能ではなく、日々の習慣と意識で育てられる。建設業という現場でこそ、この思考は真価を発揮する。
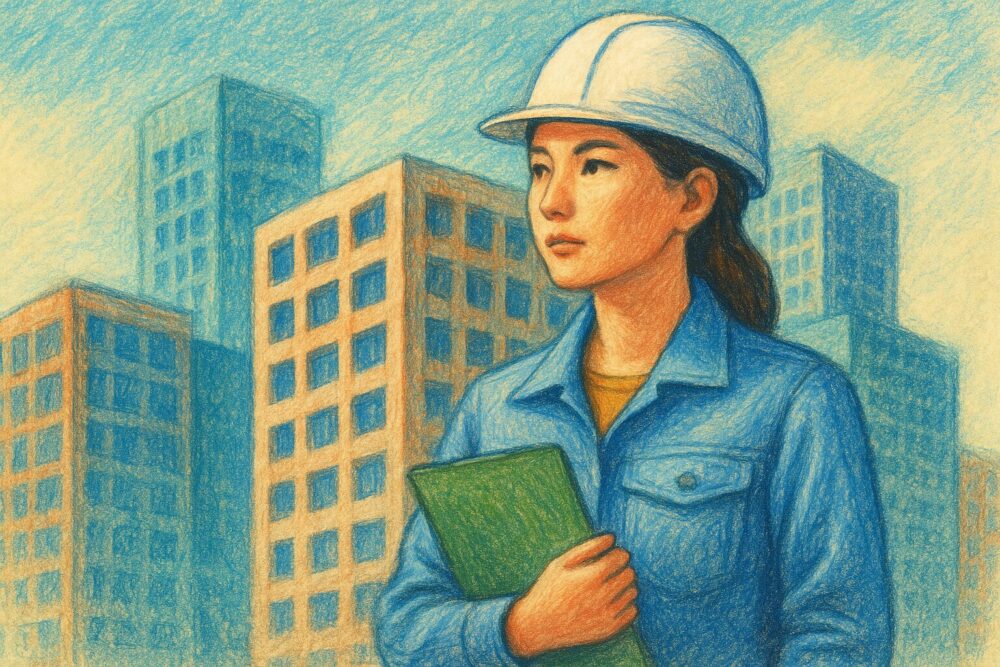
コメント