☑️当ページのリンクには広告が含まれています。
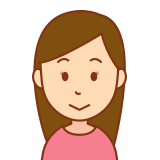
お兄ちゃん……聞いた? お父さん、肺がんだって…。しかもお母さんは要介護3で、今まで以上にケアが必要って言われちゃった。
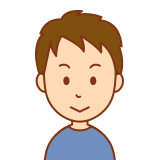
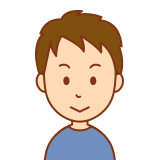
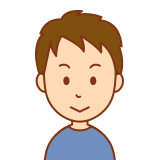
そうか…。俺、仕事の都合で遠くに住んでるから、なかなかすぐには帰れない。どうやって2人を支えていけばいいんだろう…。正直、何から始めればいいか分からないな。
大切な家族に「がん」という診断が下された瞬間、時間が止まったかのような感覚になる。それが現実のことだと理解するまで、心は混乱し、頭の中は真っ白になる。ましてや、母親が要介護3という状態なら、その負担は計り知れません。
長男は遠方に住み、頼れるのは近くにいる長女だけ。どう支えていくべきなのか、何を優先して動けばいいのか、役割分担はどうするのか──。そんな問いが次々と頭をよぎり、不安と責任に押し潰されそうになる日々が始まります。
でも、そんな戸惑いも不安も、すべて「家族を想う」あなたの優しさの証拠なんです。逃げずに向き合おうとしているその姿勢が、すでに素晴らしい一歩です。
本記事では、「父が肺がんと診断され、母は要介護3の状態」という現実の中で、どんなふうに準備を進め、家族の毎日を支えていけばよいのかを、具体的かつ実践的にお伝えします。
医療スタッフとの関わり方、公的支援制度の使い方、そして何より「自分ひとりで背負わない」という考え方──。ひとつひとつ、あなたの心に寄り添いながらお届けします。
どうか、この文章を通して「あなたは一人じゃない」と感じてもらえたらうれしいです。まずは一緒に、今できることから考えていきましょう。
がん告知を受けたときの心の動き
まずは、父親が肺がんと診断されたとき、多くの家族が感じる「心の動き」について見ていきます。ショックのあまり頭が真っ白になるかもしれませんが、今後のために「どんな気持ちになるのか」を知っておくことが大切です。
最初に感じる衝撃と不安
肺がんと告知されると、「大丈夫なのか」「治療はどうなるのか」という不安が一気に押し寄せます。とくに今回のケースでは、母親の介護状況も重なっており、「2人を一度に面倒を見るのは無理かも」「遠くに住んでいる長男はどう関わればいいのか」など、頭の中が混乱しがちです。
こうした強いショックや不安は、誰にでも起こる自然な反応です。まずは「混乱してしまうのは当たり前」と受け止めて、自分を責めないようにしましょう。
受け入れるための心がまえ
告知直後は、父親本人も頭の整理がつかず、不安でいっぱいのはずです。家族としては「一緒に話を聞こう」という姿勢が大切になります。医師の説明を長女が中心になってまとめたり、長男も電話やオンラインで情報共有に参加したりすると、全員が同じ情報を把握できます。
「家族全員が同じ方向を向けるようにする」ことは、不安を減らす大きなポイントです。肺がんにはさまざまな治療法やステージがありますから、できるだけ正確な情報を集めながら、今後のプランを考えていきましょう。
告知直後は精神的に落ち込みやすい時期ですが、この段階で「必要な情報をどう集めるか」「どんな体制で話し合うか」を決めておくと、後で大いに役立ちます。次の章では、日々のサポート方法と心のケアについて、より具体的に考えていきます。
家族ができるサポートとは
父が肺がんの治療を受けながら、要介護3の母のケアをするとなると、日常生活はどうしても慌ただしくなります。ここでは「日常生活の支援」と「心のケア」について、それぞれどのように取り組めばいいか見ていきましょう。
国立がん研究センター「がん統計」
https://ganjoho.jp/public/qa_links/report/statistics/index.html
※日本におけるがんの発症率や生存率の統計データを提供
厚生労働省「介護保険制度について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/
※介護費用の負担額や介護保険の適用範囲について詳しく解説
日常生活の手助け
母親が要介護3の場合、食事や入浴、排泄など、日常的に介護が必要になる場面が多いかもしれません。さらに、父親自身が抗がん剤や放射線治療で体力が落ちると、普段の生活だけでも大変です。そこで、
- 役割分担を明確にする:長女が定期的に自宅を訪問し、母親の介護や父親の通院に付き添う。長男は離れていても、家計管理や手続き関係を手助けするなど、遠方からサポートできる部分を担当する。
- 必要に応じてヘルパーやデイサービスを利用する:介護保険サービスを活用すれば、長女の負担を軽減でき、父親の治療にも集中しやすくなる。
このように、一人だけで頑張りすぎない仕組みを作ると、精神的な余裕が生まれます。
心を支えるコミュニケーション
父親は自分の病気だけでなく、「母親をどうしよう」という心配も抱えがちです。そのため、家族が「大丈夫、みんなで乗り越えよう」「必要なら、サービスをうまく使って少しでも楽になろう」と声をかけるだけでも、気持ちが和らぎます。
また、母親に対しても「何か困っていることはない?」と定期的に聞いてみましょう。要介護3の状態だと、ちょっとした体調の変化や気持ちの落ち込みが大きくなることもあります。些細な変化を見逃さないよう、こまめにコミュニケーションをとることが大切です。
家族だからこそ、「できる限り助けたい」と思う気持ちは強いでしょう。しかし、長女や長男がオーバーワークになると、かえって支えられなくなる可能性もあります。次の章では、医療スタッフとの連携と情報の整理について解説します。
もしも突然、がんを告知されたとしたら。 [ 樋野 興夫 ]
医療スタッフとの連携と情報収集
肺がんの治療には医師や看護師、薬剤師など、多くの専門家が関わります。さらに、介護の分野ではケアマネージャーやヘルパーなど、多彩なスタッフが存在します。これらの専門家とうまく連携し、必要な情報をしっかりとまとめることが重要です。
医師とのコミュニケーション
父親の治療方針や検査結果を理解しやすくするには、長女が主に同席し、長男は電話やビデオ通話を通して同じ情報を共有すると良いでしょう。以下のポイントを意識すると、話がスムーズになります。
- 質問は事前にメモしておく:難しい専門用語が多いので、あらかじめ聞きたいことをまとめておくと、説明が分かりやすくなる。
- 医師の言葉を整理してノートに記録:治療の方針や副作用、今後のスケジュールなどを書き留め、長男とこまめに共有する。
医師に遠慮は不要です。聞きたいことがあれば積極的に質問しましょう。
介護スタッフとの連携
母親の介護には、ケアマネージャーが中心になってプランを立ててくれます。ヘルパーさんの訪問スケジュールやデイサービスの利用頻度など、具体的な計画を練ることで、長女の負担を減らすことができるでしょう。
また、父親の治療スケジュールに合わせて介護サービスを調整できる場合もあります。介護スタッフには遠慮せず、「ここが大変」「ここを助けてほしい」と伝えることが大切です。小さなことでも相談しながら、一番負担の少ない形を目指していきましょう。
医療や介護の専門家と連携することで、家族だけで抱え込まなくても済むようになります。次は、公的な支援制度や地域のサービスを活用する方法を見ていきます。
公的制度と地域のサポート
肺がん治療や要介護のケアには、医療費や介護費用がかかります。さらに、日常生活のサポートも必要です。こうした負担を減らすために、公的制度や地域サービスを活用してみましょう。
経済的負担を軽くする高額療養費制度など
抗がん剤治療や手術費用が高額になる場合、「高額療養費制度」を利用すれば、自己負担の上限を超えた分が後から戻ってきます。長男が遠方に住んでいても、郵送で手続きできることが多いので、手続きを分担することが可能です。
また、母親の介護では、要介護3以上だと使えるサービスが増えます。利用料金の自己負担も一定割合で済むので、どんな介護サービスを受けられるのか、ケアマネージャーや市町村の窓口で確認してみましょう。
地域の相談窓口やサポートグループ
地域には「がん相談支援センター」や「介護相談窓口」がある場合が多く、経済面だけでなく、心理的な悩みにも対応してくれます。長男は電話相談、長女は直接窓口に出向くなど、役割分担して情報を得るのも良い方法です。
さらに、がん患者やその家族が集まるサポートグループに参加すると、同じ境遇の人たちの体験談を聞くことができます。家族だけでは思いつかない対処法や心構えを学ぶことも多いので、時間が合うようなら活用を検討してみましょう。
制度やサービスをうまく使うことで、家族の負担は確実に軽くなります。次の章では、ここから先の長い道のりをどうやって前向きに進むか、家族の心構えを中心に考えてみましょう。
前向きな未来を信じて過ごすために
父のがん治療は長期間にわたることもあり、母の介護はさらに生活に大きな影響を及ぼします。そんな状況でも、焦らずに「今できること」を少しずつ進めることが大切です。
一歩ずつ進む心構え
「がん」という言葉を聞くと、最悪の事態ばかり想像してしまうかもしれませんが、医療は進歩し続けています。最新の治療法や薬剤を知ることで、不安が少し和らぐこともあるでしょう。焦ってすべてを完璧にしようとせず、少しずつ父の治療や母の介護に必要なことを整えていく姿勢が大切です。
また、遠方に住む長男も、電話やオンラインで父や母の声を聞く、定期的に連絡をとるなど、できるサポートを続けるだけでも、家族としての一体感が生まれます。
家族の絆を深めるチャンス
辛い出来事ではありますが、これを機に「家族同士の絆が深まる」可能性もあります。普段はなかなか素直に伝えられない感謝や思いやりを言葉にしてみることで、お互いが安心できることも多いのです。長男、長女が協力し合って両親をサポートしている姿は、父や母にとって心強い支えになるはずです。
まとめ
父が肺がんと診断され、母は要介護3という状況は、家族にとって大きな試練です。しかし、医療スタッフや介護スタッフと連携し、公的制度を活用しながら、家族全員が役割分担をすることで、負担は確実に軽くなります。
大変なときには、「助けを借りることは悪いことじゃない」と考えてください。長女の近距離でのサポートと、長男の遠方からのバックアップが組み合わされば、乗り越えられる課題も多いはずです。どうか諦めず、希望を持って歩んでいきましょう。その一歩一歩が、ご両親にとっての大きな力になるはずです。
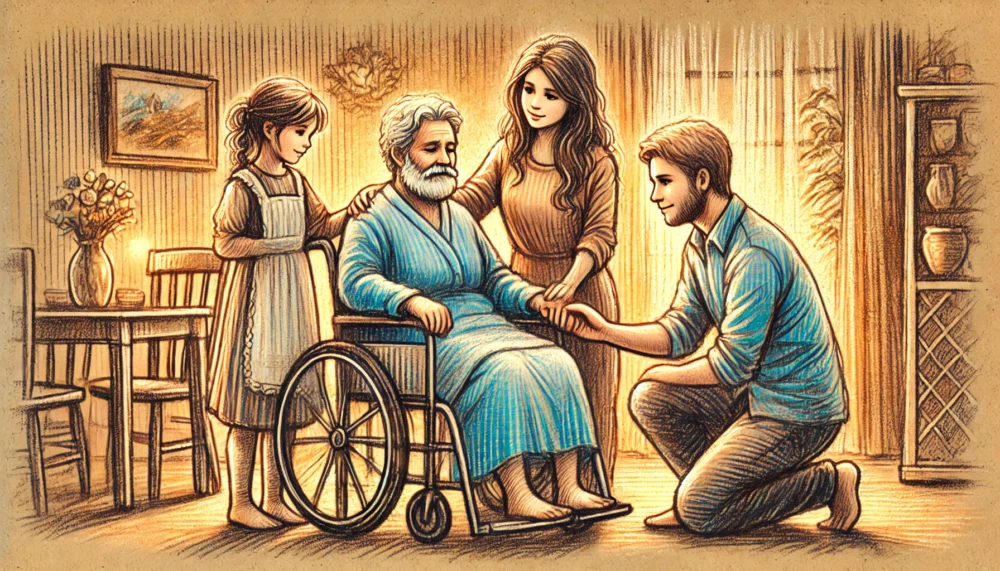
コメント