建設現場や営業所の管理職として、こんなふうに言われた経験ありませんか?
「もっと現場の様子をよく見てあげて」
「若手作業員の状態を把握して、適切にフォローして」
頭では分かっていても、実際どうすればいいのか分からない…
そんな悩みを持つ所長や主任の方は多いです。
私自身、現場代理人として働き始めた頃はまったく同じでした。
「見る力(観察力)」は、作業効率や安全管理を大きく左右する土台です。
この記事では、現場や営業所を支える管理者として、部下や職人との関係性を築くための「観察力」について、具体例を交えて解説します。
部下を「見る」って、どういうこと?
「現場の様子を把握して」
「作業員の動きや表情をよく観察して」
現場のベテラン職人や上司に、よく言われるフレーズです。
でも、正直なところ…
「いや、どうやって見るの?」
「自分の作業でいっぱいいっぱいだよ…」
私も最初は同じでした。
センスのある現場監督は、自然に職人の気持ちを察して適切にフォローします。
でも、多くの管理職は、経験とともにそれを習得していくものです。
日報の処理、材料の発注、施主対応、クレーム処理…
目の前の仕事に追われながら、部下にまで気を配るのは至難の業。
とはいえ、「誰かが気づいてくれるだろう」と放置してしまえば、 小さな違和感がやがて事故や退職といった大きな問題に繋がることもあります。
だからこそ、この記事が「現場管理に悩むあなた」の力になれたら嬉しいです。
「観察力」があると、現場はどう変わるのか?
観察力とは、「相手の行動・表情・発言から内面を読み取り、事故やトラブルを未然に防ぐ力」です。
この力が身につくと、管理者として以下のような変化が現れます。
- 若手の成長スピードが上がる
- ヒヤリハットの予兆に気づける
- ベテラン職人との信頼関係が深まる
- 現場の空気がよくなる
たとえば、「最近道具の扱いが雑な新人A君」について、
- ただ叱るのではなく、「背景に何があるのか」を探ることで、
- 実はプライベートで悩みを抱えていた、ということもあります。
また、こんな事例もありました。 ある日、いつも明るく声が大きいBさんが、朝礼の声が小さく表情も曇っていました。 そのままにしていたら、その日午後に持病の腰痛が悪化し、作業中に転倒してしまいました。
「あのとき声をかけていれば…」と、あとから後悔する前に 日々のちょっとした違和感に敏感になることが大切です。
観察力は、現場を守る「予防保全力」です。
「思い込み」が観察の邪魔をする
私の経験からも、レッテルによる判断ミスは多々あります。
- 「あの子はとろいから時間がかかる」
- 「この人は職人気質だから口出し無用」
こういった思い込みが、本当の課題を見えなくしていたのです。
たとえば、ミスが続いた若手を「要領が悪い」と決めつけていたら、 実際は道具の使い方を教わっていなかった、というケースも。
また、施工図を読めないまま現場に出されていた新人が、 ミスを連発して「なってない」と怒られていたこともありました。
一人ひとりの「変化」を見逃さないことが、現場の安全と品質につながります。
観察力を高めるための5つの行動(現場編)
具体的に何をすればいいか? まずはこの5つから始めてみてください。
1. 昼休憩中に声をかける
「最近どう?」という何気ない会話がヒントになります。
現場では忙しくて立ち話も難しいので、昼休憩や道具の整理中がチャンスです。
「暑さ、きつくないか?」「今の作業、やりにくくない?」
こんな声かけから、若手の本音がぽろっと出ることも。
さらに、休憩所でのちょっとした仕草(ため息、スマホをずっと見ているなど)も 観察ポイントです。
2. 作業中の「動きの違和感」に注目する
体の動きがぎこちない=体調不良のサインかも
重い腰、動きが遅い、道具の持ち方が変…
そういった小さな変化に気づくことで、事故を未然に防ぐことができます。
特に連日の猛暑日や繁忙期は、 集中力や体力の低下が顕著に現れるので要注意です。
3. 月単位での変化を記録しておく
月初と月末で態度や成果がどう変わったか?
日々の忙しさで忘れがちですが、振り返るために記録しておくことは有効です。
スマホのメモでも良いので、月1の簡易レビューを習慣化すると◎。
この記録は評価面談や面談時の根拠にもなります。
4. 他の班長や営業所長と意見を交換する
他現場の情報もヒントになる
現場が変われば、同じ人でも違う顔を見せます。
他の担当者と共有することで、「なるほど、うちだけの問題じゃなかった」と気づくことも。
横のつながりを活かした情報共有が、観察力を補完してくれます。
5. 作業報告やメール連絡後の様子を観察する
報告後の表情に注目してみましょう
きちんと報告メールを送ってきたのに、実際に会った時に不安そうだったり、元気がなかったりすることがあります。
メールや文面でのやり取りと、実際の様子が一致していない時こそ、要注意です。
返信がやけに遅い、内容がそっけない、形式的な定型文のみになっている場合なども、サインと捉えましょう。
結局、大事なのは「想像する力」
観察力の本質は…
**「相手の立場に立って、想像をめぐらせる力」**です。
- 「今日、暑さで疲れてるかもな」
- 「昨日の残業が影響してるかも」
- 「もしかして家庭の事情?」
頭の中で、部下や作業員の1日を想像してみるだけで、接し方は大きく変わります。
これは、施工管理でも営業でも共通する大事なスキルです。
想像することは、相手を理解する第一歩。
「きっとこうだろう」ではなく、「かもしれない」思考で接することが、信頼関係の構築につながります。
観察力を高めて、現場と人を守れる管理者に!
「よく見てやって」と言われて戸惑ったあなた。
現場を預かるあなたにしかできない「気づき」があります。
一つひとつの変化に敏感になり、事故や退職を防ぎ、 若手の定着を後押しできる存在になっていきましょう。
現場の空気を変えるのは、管理者の一言からです。
観察力は一朝一夕で身につくものではありませんが、 意識し続ければ確実に変化が起きます。
この記事が、建設業で現場や所長を支える方々のヒントになれば嬉しいです。
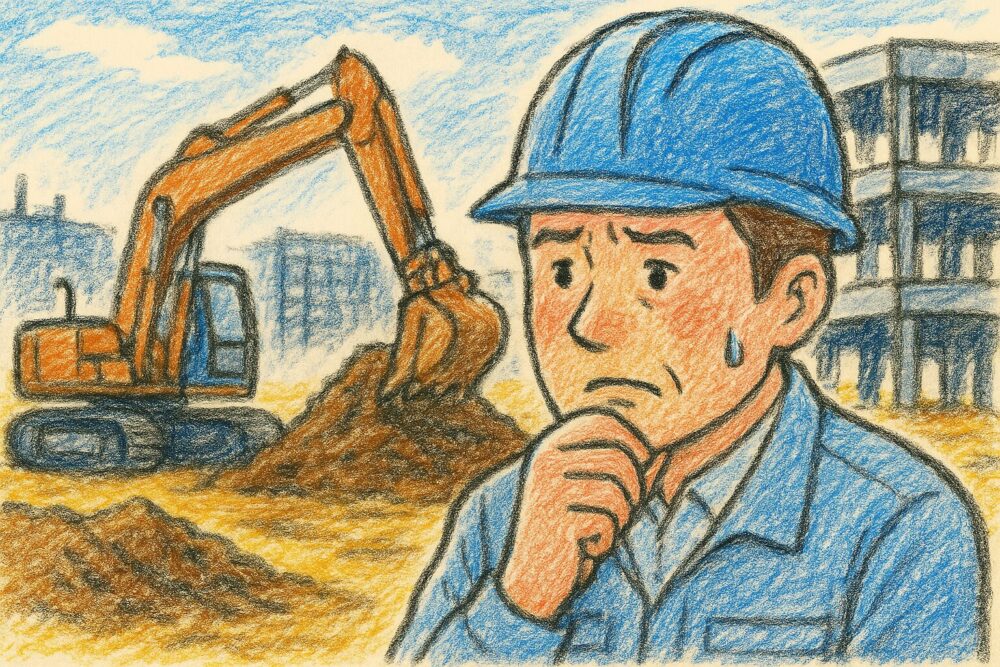
コメント